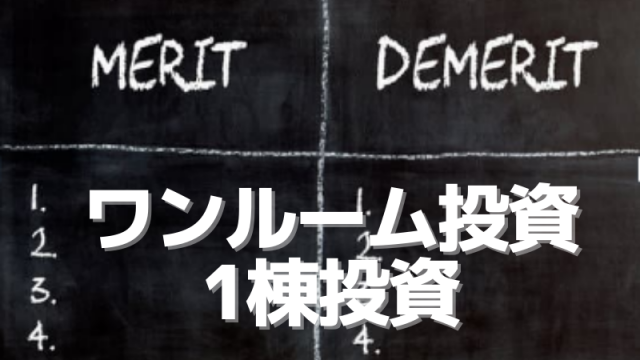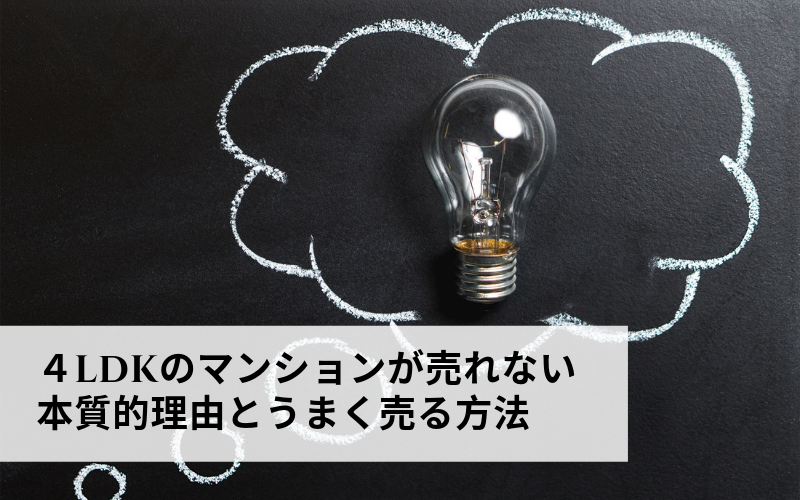新築アパート、中古アパート、ワンルーム、一棟マンション。
全ての領域で利益をあげている成功者がいる。
利益を上げられず物件を手放したひともいる。カギは「リスク」にある。
不動産投資6つのリスク
リスクの分しかメリットは生み出しにくい。
メリットだけしかない。というおいしい話、世の中にあふれているかもしれないが、それは手を出さないほうが無難。と断言しても良いかもしれない。基本的な不動産投資リスクを見ていきたい。
空室リスク
不動産投資で最もリスキーなのはこの「空室リスク」。入居者が入らなければ一気に収入がゼロになる。
融資で購入している場合、空室は収入がゼロになるだけではない。ローンの支払いは毎月続いて支出は継続することになる。マンションであれば管理費、修繕積立金の支払いも継続。年間を通しては固定資産税の支払いも。純粋に支払いだけが進んでいく。
家賃下落リスク
比較サイトやブログなどで書かれているのは、「年数がたって古くなってくれば家賃がさがる。」というもの。外れてはいないかもしれないが、家賃下落リスクとは、「需要と供給のバランス」によっておきることを理解すべきだ。
究極な例だが、どんなにボロでも、必要な人にその家しか無ければ家賃は高くても入る。同じ物件があふれ供給が過多であれば家賃は下落する。
供給過多の時は、物件が新しかったり、設備が良かったりなど「物件力」の勝負になり、いわば「競争力」が強い物件しか勝ち残れない状態となる。
古いかどうか。というよりも需要があるかないか。を将来的に予測できるか否かにリスクの大小が左右される。
家賃滞納リスク
「入居者が入っていれば家賃が入ってくる。」のが通常。しかし、何らかの理由でその人が家賃を納めない可能性もある。「家賃滞納リスク」だ。
賃借人にたいしては、借地借家法よって強く入居者が保護されている。たとえ家賃が滞納されていても退去させて次の入居者を探すことはとても困難だ。
退去には「正当事由」が必要。何をもって正当事由というかだが、究極的なことが無い限りほぼ貸主側の意見は認められないと思ったほうがいい。
仮に退去を許諾してくれた場合、次の引っ越しにまつわる費用、いわば立ち退き料を迫られる。家賃滞納は空室リスクより太刀が悪いことを知っておこう。
金利変動リスク
融資で投資物件を購入している場合、金利上昇すると毎月の支払額にダイレクトに響く。最初は良い条件の金利でキャッシュフローが出ていたとしても、金利上昇すれば入居者から賃料がはいってきていてもマイナスになる可能性がある。固定金利という商品があるが金利は通常、変動より高く設定されており、利益を生み出すための不動産投資では選択肢に入りづらい。
キャッシュフローが、購入した時のみ出ていれば良い。というものではない。どのくらいの金利上昇に耐えうるかをシミュレーションして買えていなければ泣きを見るのは近い。
災害リスク
最も起きてほしくないが起きる可能性があるのが災害リスクだ。むしろ日本であれば可能性は高いと思っておいたほうがいい。
地震で建物被害をうけたり、雨や海からの水害を受けるなどした場合、入居者の退去、引っ越し、建物の修繕などが起こり多大な損失を受ける。
倒壊や火災という最大限の被害にあった場合には建物価値は一気にゼロ。入居者もゼロ。収入が途絶える上に修繕費が重くのしかかる。
事故物件
事故物件はいわゆる「心理的瑕疵」と呼ばれる。部屋の中で亡くなったり、殺人や自殺などの事件性の事象がおきたり。といったもの。一般的に心理的瑕疵と言われている。
「心理的瑕疵」に該当するかどうかは次に住む人の受け取り方次第であるが、一度心理的瑕疵の物件だとなると、長い期間入居者が決まりにくくなったり、賃料を格安に下げないと決まらなかったりするのが通常だ。
どうする。対策は?
リスクをつらつらと並べてきたが、私は不動産投資を続けている。
それぞれに対策はある。それをできれば不動産投資に動いて良い。それが向いていなければ別の投資に動いたほうが良い。
空室リスク対策
空室リスクを軽減するには「入居者がすぐ決まりそう」な魅力をできる限りそろえること。
- 立地はどうしようもない。最初に場所選びを間違わない。
- 適正賃料、エッジの効いた間取り。のような「入居率が高そうな武器」を採用する。
- 入居者が「入ってくれた理由。退去の理由」を理解し能動的に対策する。
- 単身向けが入ってくれる。学生が入ってくれる。女性が入ってくれる。それには理由がある。その理由をキャッチアップし自分の物件ターゲットを明確にし対策する。
- 早めに退去情報が入ってくるルールを敷き、次の入居付けに迅速に動く。
- 各ターゲット向けに特化して広告。広告料をつけるなど、「経営者」として頭をつかう。
というものだ。空室は不動産経営で基本中の基本なので重点的にリスク回避に努めたい。実際にその運用をするために、「真のアドバイザー」がいればもっと具体的に対策も可能だろう。
家賃下落リスク対策
家賃を下げて安いことも、物件がきれいなことも、ピアノ可、ペット可も「物件力」「競争力」の要素となる。
基本の王道は上記の通り「立地」がいいこと。
立地。というのは駅が近い。だけではない。人それぞれだ。
学校が近い。スーパーが近い。ペット可物件で動物病院が近い。など、購入物件を見極めるときに必要なのは、物件が高い、安いだけではなく、将来にわたって勝てる「その優位性」を見極められるかどうかだ。
老朽化による家賃下落の対策は、リノベーションで回復する。
場所や利便性といった「立地」はどうしようもない。一番最初の物件選定ポイントは明確だ。
利回りは少々下がるが、サブリースが使える物件であればそれも選択肢に入るだろう。
家賃滞納リスク対策
一番メジャーなものは「家賃保証会社」を使用して入居者の審査を行うこと。そもそも審査基準があがり、ある程度の人しか通過できない。
また、もし入居者が滞納しても、家賃保証会社が6か月~24か月(プランや会社によって異なる)で家賃を肩代わりして大家に振り込んでくれる。滞納分は家賃保証会社が入居者に請求をし続ける。
二番目には「信頼できる賃貸管理会社」を選ぶこと。保証会社をつかえばその審査の目は厳しいが、賃貸管理会社がしっかりしていれば、ここでもある程度の入居審査ができる。
上記で述べたサブリースを利用するのももちろん手だ。
金利変動リスク対策
緩やかな上昇志向になってきている金利。固定金利であれば乱高下の影響は受けないが、そもそも金利の設定が高い。
変動金利、固定金利を組み合わせてリスクに対応するか、変動金利一本で組んでいる場合、金利の高いものから自己資金を入れて繰り上げ返済をしていくのが王道だ。
大きく上がれば大打撃だが、毎月の支払いが一部屋分の賃料くらい上がる。ということはない。空室リスク、滞納リスクをどれだけ回避するかが金利リスクよりは重要だろう。
災害リスク対策
日本で不動産を持つなら避けては通れないワードだ。
木造を購入するなら新耐震基準、もしくは劣化等級3級や2級といった基準を取得取得しているものが地震に対する備えとしては有効だ。
海岸や水辺に近いところであれば、2、3階以上のマンションを購入したり、一棟アパートなどであれば少しでも高台、基礎の立ち上がりを少し高くしておく。などの工夫ができる。
中古を購入する場合、築浅、RC造、地盤の固いエリアかどうか。もポイントだ。
ここで注意すべきはアグレッシブに利回りを取りたい場合は上記の真逆を選んでいくことになる。そういう投資家も存在する。
安全であれば安全であるほど利回りも安全でさほどとれないことは認識しておくべきだろう。
損害をカバーする「火災保険、地震保険」の加入がなんといってもリスク回避には一番かもしれないが、結構金額が張る。安定タイプかアグレッシブタイプかで選択していけば良い。
いかようにでもリスクを回避する方法はある。やるか、やらないかのみだ。
地震の災害リスクマップ、水害のハザードマップ、それらを見て場所を選ぶのもいいが、日本はどこも災害マップでは真っ赤。ハザードマップでは真っ青。それで選んでいては先に進めない。
このようなことから、物件購入の前に地域の災害リスクを調べておくとリスクを理解したうえで投資ができる。
事故物件対策
これは事前の対策というのがなかなか難しい分野だが、賃借人の審査・選定に気を付けることはしておいた方が良いだろう。
治安の悪そうな場所であったり、問題がありそうな入居者かどうか判断を委ねたり、アンテナを張っておくことしかできないが入り口でアンテナを張っておけば最小限になる可能性は高い。
まとめ
以下はリスクではなくランニングコスト。かかるかも。ではなく、必ずかかる経費として組みこんでおけば対策しやすい。
<建物に関して>
- 10年前後 鉄部の塗装、外壁塗装、シーリング、屋上防水
- 20年前後 建具、給排水管の交換、補修
<建物内設備に関して>
- 15年前後 キッチン、浴室の換気扇、ガスコンロ、エアコン、給湯器
- 25年前後 フローロング、居室内の給排水管
- 35年トイレ、キッチン、浴室
リスクを知らずにはじめ、あとからマイナスになっていく経営がとにかく多い。これらはまだ一部かもしれない。
不動産投資はリスクだらけ。物件よりも、できる限りリスクを表面化してくれるアドバイザーと出会うことが、逆に安心して不動産投資を始められるファクターになる。